介護保険制度ってどんな制度?
介護保険制度とは、加入者が保険料を出し合い、介護が必要なときに要介護認定を受けて、必要な介護保険サービスを利用することができる制度のことです。40歳になると全ての国民は介護保険に加入し、生涯、介護保険料(※1)を納め続ける義務があります。
(※1)負担すべき保険料は、収入や市区町村によって異なります。
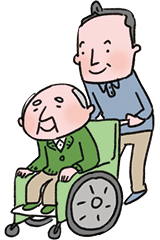
介護保険制度では、介護をサポートするためのさまざまなサービスを、1割負担で利用することができます。ただし、収入が一定以上(年金収入のみの場合は、年金収入280万円以上)の場合は、自己負担率が2割~3割になります。
保険料の支払いや金額はどうやって決まるの?
介護保険の加入者は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳~64歳までの方)に分類されます。
65歳以上の第1号被保険者は、原則として年金からの天引きで市区町村が保険料を徴収します。40歳~64歳までの第2号被保険者は、加入している健康保険と一緒に保険料を徴収されます。
会社員などの健康保険に加入している方
給与などの収入に介護保険料率をかけた総額を、事業主と被保険者で1/2ずつ負担します。介護保険料率は、所属する健康保険組合ごとに違います。
| 介護保険料 = 「標準報酬月額」×「介護保険料率」 |
|---|
自営業などの国民健康保険に加入している方
国民健康保険の介護保険料は、医療保険料に上乗せする形で、国民健康保険税と合わせて、居住している市区町村が徴収しています。
これは自治体独自の計算で決まり、主に所得や財産などで変わります。それぞれの市町村で計算は違いますが、以下の式で計算されます。
| 介護保険料 = 「所得割」+「均等割」+ 「平等割」+「資産割」 |
|---|
|
「所得割」と「均等割」のみ、「所得割」と「均等割」と「平等割」の3区分のみなど、自治体によって組み合わせもさまざまで、計算方法も変わってきます。
介護保険料は40歳以上であれば、無職でも支払わなければいけません。ただし、被災した場合や、失職・廃業などによって収入が激減した場合、生活が困窮している場合は、介護保険料が減免されます。
介護保険サービスを利用できる人は?
介護保険サービスを受けられるのは原則として第1号被保険者である65歳以上の人です。ただし、加齢によって生じる16種類の「特定疾病」と診断された場合に限り、第2号被保険者である40歳~64歳までの人も介護保険サービスの利用ができます。
| 年齢 | 区分 | 要件 |
|---|---|---|
| 65歳以上の人
|
第1号被保険者 |
|
| 40歳~64歳までの人
|
第2号被保険者 | 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。 |
介護保険で対象となる16種類の「特定疾病」
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)
また、介護保険サービスは、介護保険で利用できる1ヶ月の上限額が要介護度によって決まっています。これを介護サービス利用限度額といいます。
| 区分ごとの介護サービス利用限度額 (1ヶ月あたり) |
|
|---|---|
| 要支援1 | 50,030円 |
| 要支援2 | 104,730円 |
| 要介護1 | 166,920円 |
| 要介護2 | 196,160円 |
| 要介護3 | 269,310円 |
| 要介護4 | 308,060円 |
| 要介護5 | 360,650円 |









