症状別の対処のヒント
認知症の代表的な症状ごとに、対処のヒントを紹介します。
(1)夕方になると家を出ようとする
その方にとっては今、自分が住んでいるのは「昔の自分の家」なので、夕方になると「ここは自分の家じゃない、よその家に長居してはいけない」という気持ちになると考えられます。

対処のヒント
「もう少しゆっくりしていってください」「夕食も食べていってください」などと声をかけ、空腹を満たしたり好きな手仕事などに誘ったりして、落ち着くのを待ちましょう。
(2)「物を盗られた」という妄想にとらわれる
認知症で起きやすい被害妄想のひとつに、物を盗られたと訴える「物盗られ妄想」があります。自分でしまったことを忘れてしまい、盗まれたと思うのです。介護をしている人が犯人として疑われやすい傾向があります。
対処のヒント
否定せず話をよく聞きましょう。一緒に探したり、探している途中で話題を変えてみたり、第三者に間に入ってもらうことで落ち着くこともあります。
(3)空腹を訴え続ける
認知症の症状として、異常な食欲を示すケースがあります。食べたことを忘れてしまうだけでなく実際に空腹を感じているので、何か食べるまで納得できません。
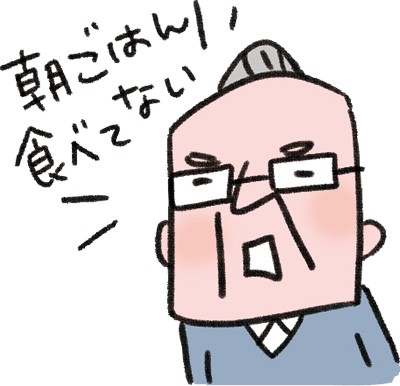
対処のヒント
「今仕度をしているから、これを食べていて」とおにぎりなどの軽食を渡すと良いでしょう。我慢させて混乱をまねくよりは、食べさせた方が落ち着いた状態を維持できます。
(4)攻撃的になる
いろいろなことがわからなくなったり、出来なくなることへの不安や焦りなどから、興奮したりかんしゃく・暴力を起こしてしまうことがあります。

対処のヒント
本人を追いつめないことが大切です。かんしゃくや暴力が始まってしまったら、落ち着かせることを最優先に考えましょう。
認知症の予防方法
認知症は、生活の環境や習慣に大きく関係しているといわれています。規則正しい生活に加え、脳に刺激を与えたり、活性化をうながす行動は、認知症の予防につながるといえます。
(1)運動
週3回30分以上の運動を行っている人は、行っていない人と比べて認知症発症のリスクが40~50%下がっていると報告されています。 散歩・ストレッチ・ヨガ・水泳など、趣味と兼ねて出来るものがあると良いでしょう。

(2)食事
抗酸化作用があるポリフェノールは認知症予防に効果があるといわれており、野菜・果物・魚類・豆類・オリーブオイルなどを取り入れるのが良いとされています。食べ物を細かく噛むことで胃の中の消化を助けるとともに、噛むときの振動が脳を刺激し、良い効果をもたらします。

(3)知的トレーニング
知的トレーニングとは、パズル・計算・暗記・間違い探しなど脳を使うトレーニングです。ゲーム感覚で楽しめるものも多いので取り組みやすいでしょう。日記を書く、新聞を読むといったことも十分な知的トレーニングになります。農作業や料理も、手先と頭を同時に使うので効果が期待できます。

(4)コミュニケーション
他人との交流は脳を刺激し、生活に豊かさをもたらします。家族と会話をする、仲間と交流する、共同作業を行うといった機会をもつことが大切です。
パチンコや将棋など好きな趣味があれば、それを続けられる環境を整えることも認知症予防になります。大切なのは、無理なく楽しみながら続けられることです。

認知症の介護ストレスを軽くするために
認知症は突然発症するケースが多く、どの家庭でも戸惑いや混乱が起こり、介護者には大きな精神的負担がかかります。
介護者の負担を軽くするために大切なこと
- 介護保険サービスなどの高齢者支援サービスを利用する
- 専門的なことを相談できる相手を探す
- 外部とのつながりをもつ
自分の生活の全てを介護のために費やさないようにすることも大切です。
デイサービスやショートステイを利用し、時間ができたら自分の趣味や好きなところに出かけるなど、介護生活にもオンとオフを作りましょう。
介護仲間を作ることもリフレッシュ効果があります。介護のことを話すことができて、自分を認めてくれる仲間がいると、孤立感から解放されやすくなります。
大切なのは、認知症の方を支える家族が笑顔でいられることです。家族や周囲の人が無理をせず笑顔でいること・不安を抱え込まないことは、認知症の症状を和らげる効果もあるといわれています。







