現代日本が直面する超高齢社会
日本の高齢者人口は、団塊世代が65歳以上となった2015年に3,387万人に達し、総人口の27.3%を占めました。さらに2025年には75歳以上の後期高齢者が4人に1人の割合になると予想されます。
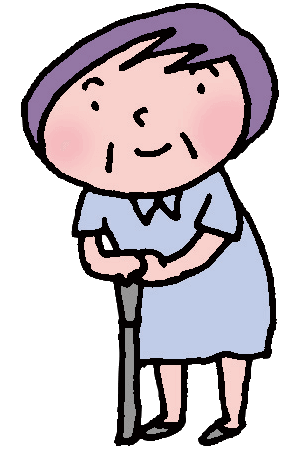
このような超高齢社会を背景に、2000年から介護保険制度が始まり、家族の介護負担は軽減されましたが、高齢化と少子化が進み、介護保険や医療保険などの公費だけで高齢社会を支えるのが難しくなってきました。
そのため厚生労働省は、団塊世代が75歳以上となる2025年を目途に、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域内でサポートし合う体制「地域包括ケアシステム」の構築を推進しています。
2025年に高齢者の数と認知症の人の数が、今よりも確実に増えると予想されることから「2025年問題」と呼ばれています。
地域包括ケアシステムとは
地域包括ケアシステムとは、各地域に住んでいる高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい生活を人生の最後まで持続できるように、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援などのサービスを、日常生活圏域(自宅から30分以内)で一体的に提供することを目指す体制のことです。

この体制の実現のためには、自助(介護予防への取り組みや健康寿命を伸ばすなどの自分自身のケア)、互助(家族や親戚、地域での暮らしを支え合い)、共助(介護保険・医療保険サービスなどの利用)、公助(生活困難者への対策として生活保護支給などを行う行政サービス)という考えに基づき、地域住民・介護事業者・医療機関・町内会・自治体・ボランティアなどが一体となって地域全体で取り組むことが求められています。
地域包括支援センターとは
この地域包括ケアシステムの実現に向けて大きな役割を担うことになるのが、「地域包括支援センター」と「ケアマネジャー」です。

「地域包括支援センター」とは、住み慣れた地域で生活を続けられるよう高齢者の暮らしを地域でサポートするために、市区町村の各自治体が設置する拠点です。
地域包括支援センターには、ケアマネジャー・保健師・社会福祉士が在籍しており、介護だけでなく医療・福祉・健康など、さまざな相談の受付や情報提供を行っています。高齢者とその家族の悩みや心配ごとの解決方法を提案してくれたり、各市区町村が実施する介護予防プログラムを紹介してくれたりします。
ケアマネジャーの役割
「ケアマネジャー(介護支援専門員)」は、介護に関する専門職であり、介護が必要な人やその家族と相談し、在宅や施設で適切なサービスが受けられるように、ケアプランの作成や県警機関との連絡や調整を行います。
ケアマネジャーの仕事は、利用者とサービスをつなぐコーディネーターの役割を担っており、地域包括ケアシステム現実のための中核的な存在といえます。
ケアマネジャーの主な仕事
- 介護保険の申請代行
- ケアプランの作成
- 介護に関わる各種手続き
- 市区町村や介護サービス提供者との連絡や調整 など







